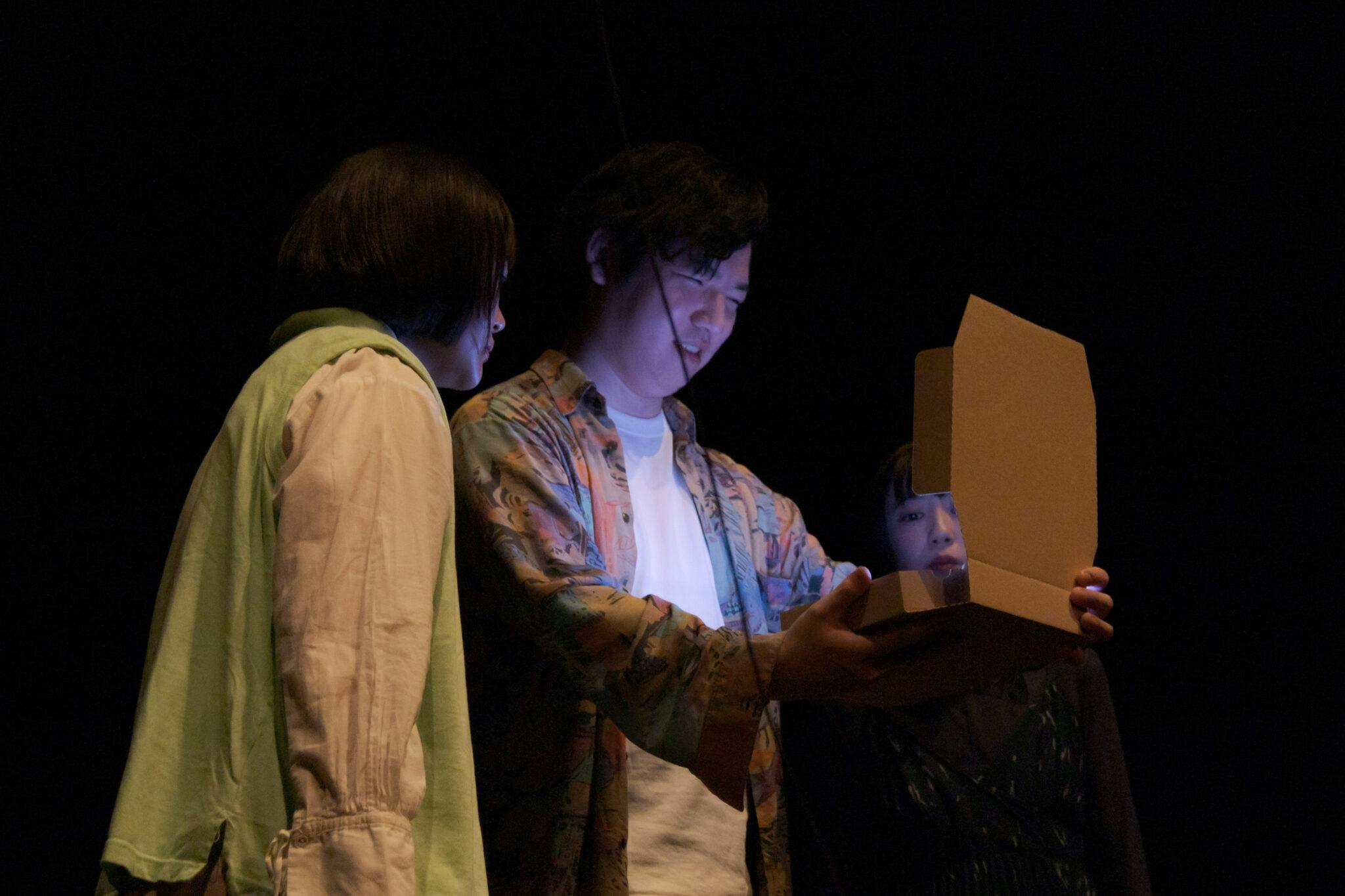※掲載の文章は、第15回せんがわ劇場演劇コンクール表彰式の際の講評を採録・再構成したものです。
第15回せんがわ劇場演劇コンクール【講評】老若男女未来学園『もういい、俺は死後評価されるタイプの芸術家で』


【小笠原 響】
演劇という虚構の世界が現実とどう立ち向かっていくのか、ということを大きな命題として取り扱った作品だったと思います。
劇場の緞帳が開いて始まるというコンクールの条件を、カーテンが開いて目を覚ますという脚本上の設定とリンクさせ、冒頭から劇のリアリティを高めていました。舞台に吊られた仕掛けからポタポタと落ちるパチンコ玉がどんぐりだという設定も面白かったし、鉄の玉が舞台に落ちる音が圧倒的なリアリティを醸し出していた。落ちたパチンコ玉を箒と塵取りで集める音、ピーナッツをかじる音、こういった圧倒的な「物」のリアリティに対して俳優のセリフ・演技がどう抗えるのか、というところをとても興味深く観ていました。
バスを待つ人々の前にガーフィールドの電話機が走りこんでくる辺りから劇は急速に、リアリティの世界から虚構の世界に変化していきました。バスを待つという行為とピザを待つという行為を比較する場面も、別役作品的ななつかしさと、現代性とが混ぜ合わさり面白かったです。
劇の後半で、リアリティに対して作品がどういう風に決着をつけるのか、もう一歩踏み込めたら良かったと感じました。ガーフィールドの電話が再び現れ、受話器から待ち続けた人からの声が聞こえるというラストも面白いと思いましたが、大事な電話というアイテムがガーフィールドのデザインであった為、キャラクターのインパクトの方が勝ってしまったのは誤算であったかもしれません。
【生田 みゆき】
冒頭で「ここは劇場だぞ」というところから始まって、作者は嘘が嫌いなんだろうなと思いながら観ていました。それは俳優の喋り口にも現れており、普段演出者として私が俳優に要求している「キーワードになるところは立てて(目立たせて表現して)」というようなことに対して、意地でもそんなことしてやらないぞ、意地でも淡々としゃべってやるという批評的な目線を感じました。丁寧で親切なんだけど嘘っぽかったり、いかにも芝居っぽい表現方法がしたいわけではない、そうでない表現をやっていくんだという意思をすごく感じました。本当に羨ましい、素晴らしいなと思いながら観ていました。
そういう表現がベースにあるということはつまり、観客が劇世界へ誘導してもらえない。誘導してもらえないことの心地よさや愉快さは、迷子になりやすいという側面もあると思います。最初はどんぐり(パチンコ玉)の音の仕掛けをどうやっているのかという面白さもあって集中して観ていたんですが、途中からは俳優の喋り口に慣れてきたというのもあって、「これをどう見ればいいんだろう」とか「これは何を訴えたいんだろう」と考えながら見ていました。
劇世界への興味関心が、誘導してもらえないがゆえに途切れてしまう瞬間もありました。ただ、そういうことも含めて、嘘をつかないということを目指しているとも思いましたので、ぜひこの後のディスカッションの時間にでも色々なことを伺えたら嬉しいです。
【松尾 貴史】
虚構とリアルの狭間を、境目をなくすのか、飛び越えて行ったり来たりするのか。イメージの実験ができるすごくいい機会をお客さんは与えられたのかなと思います。
例えば、バスを待っているときに知らない人と話すというようなことは、令和になった今はもうほとんどない。昔は「もう行きましたか」とか「どちらまでいらっしゃるんですか」とか「天気が悪くなりそうですね」という話を普通にしていたと思うんですけど、そういう状況が懐かしく感じて、でも最近の流行りのものとかも出てきて、過去と現在を行ったり来たりしている。虚構とリアルも行ったり来たりしているというような、面白い感じの脳内での遊びができたと感じました。
玉が落下してくるあの音の効果が不思議と集中させるところもあり、ランダムに落ちてきているのか、計算され尽くして落ちているのか。そんなことまで色々と考えさせられて、芸術表現としてすごく面白いことをなさってるなと思いました。
【山田 由梨】
堂々巡りの不条理な感じの会話がすごく面白くて、前半はお客さんもすごく笑っていましたね。私もクスクス笑いながら、楽しませて見させてもらいました。
この作品から私が感じ取ったのは、演劇というものに対する森さんの「態度」だったと思います。演劇の嘘をあえて露(あら)わにしていくとか、暴いていくとか。例えば、バス停の設定だったのに「ここはせんがわ劇場ですよね」と、ある意味没入させずにしらけさせていく。上から落ちてくるパチンコ玉もそういう効果でやっていたと私は受け取り、セリフが聞き取れなくなったり、玉の音が気になって会話を聞き逃したりすることが、しらけさせることを狙っているように思いました。
演劇への「態度」自体は面白いと思いましたが、一方で「その態度を持って何を見せるか」という「その先」が必要なんじゃないかと思いました。それは他の審査員の方が何を受け取っていいのかわからなかったと仰っていたのと同じようなことで、お客さんの反応にも現れていたんじゃないかなと思います。
前半はすごく笑いが起きていたけど、後半は笑いが少なくなってきたのは、やっぱり淡々としていて変化がなく、芝居も含めて、少し飽きてきてしまい、集中力が切れていってしまうということが起きていたのかなと思いました。でも「会話力」がすごくあり、面白かったです。
【徳永 京子】
知的な企(たくら)みを感じる作品でした。他の審査員の方が仰っているように、あえて淡々とした会話を続けることで(このあと何が起きるかの)興味を引いただけでなくて、これから演劇というフィクションを見ようとしている劇場の観客たちに向けて、嘘はいいのか悪いのかという根本的な質問を突きつけるところから始まったと感じます。そしてその質問を無責任な投げっぱなしにせず、山田さんの言葉を借りるなら「演劇をつくる態度」というもので示しました。
例えば、明らかな金属音に対して「どんぐり(の音)」と言うなど、セリフを聞いているこちらが常に、舞台上で起きていることが本当か嘘かの選択をさせられる。その時間は、私には「心地よい迷子の時間」でした。そして淡々と一定のリズムで進められるセリフに、不協和音的な金属音が加わることで、偶然性を受け入れ、その偶然性も作品に取り込んでいくという老若男女未来学園さんの世界観を感じました。本来なら耳障りなはずの金属音も含めて「端正な器をつくっている」ように感じられましたが、持ち時間も数分の余裕がありましたし、できれば器の外に出てくるぎょっとする何かも示してもらえたら、さらに広がりがあったのでは、と思いました。