
『ドクターズジレンマ』スペシャルトーク~佐藤誓&小田島創志&小笠原響~

台本製作真っ最中の6月某日。
せんがわ劇場芸術監督演出公演「ドクターズジレンマ」主演の佐藤誓さん、翻訳の小田島創志さんと、芸術監督の小笠原響がてい談を開催しました。
トークに先駆けて、5月にはキャスト・スタッフを揃えて、初めての読み合わせ稽古を実施。その時のエピソードや作品の見どころ、演劇の面白さを語っていただきました。
聞き手:佐川大輔(せんがわ劇場演劇チーフディレクター/鑑賞ナビゲーター)
Q まず初めに、演劇との出会いについて教えてください
佐藤誓(以下「佐藤」) 影絵で有名な藤城清治さんのケロヨンというキャラクターがあり、テレビ番組でもすごく流行っていたんですが、藤城さんの劇団木馬座がやった「眠り姫」を見たのが一番最初だったと思います。その後は、学校でやるようなお芝居を見たことはあったけれど、実際に芝居を始めようと思ったのは大学の演劇研究会で、テントを張ったアングラの芝居でした。僕は岩手の盛岡出身なんですが、そんなものは盛岡では観たことがなかったので、カルチャーショックでした。「これはすごい」と思った。唐十郎さんから、世の中がつかこうへいさんのブームになった頃に、僕らは唐十郎さんのようなアングラ芝居をやっていたんです。
小田島創志(以下「小田島」) 舞台歴は何年になるんですか。
佐藤 東京に出てきたのが26歳なので30年ちょっと。
ーー長いセリフはどのように覚えていますか?
佐藤 僕はとにかく何回も読んで、口に出して、歩きながら覚えます。家の近くに公園があるので、セリフをぶつぶつ言いながらウォーキングをしています。
小田島 職務質問とかされないんですか?
(一同笑い)
佐藤 夜じゃなく朝とか午前中なので、大丈夫です。歩きながらというのが一番いい。ギリシャ悲劇であれば立ったままずっと喋っているかもしれないが、人間は動かず喋ることはあまりないので、とにかく動きながらセリフを覚えています。
小田島 稽古開始前にセリフは完璧に覚えていくんですか?
佐藤 その時々によって違いますが、本ができていれば…(小田島 すみません。)できるだけ覚えていきますよ。セリフは最低限覚えた方が動きやすいんですよね。

ーー小田島さんはどうですか?
小田島 僕は祖父と両親が演劇の翻訳をしているので、子どもの頃から劇場に連れていってもらっていて、出会うというより知らず知らずのうちに演劇の楽しさにはまっていました。演劇の翻訳をやろうと思ったのは遅く、高校3年生のときにハヤカワ演劇文庫でハロルド・ピンターの後期戯曲集が出版され、ピンターの研究をしようと大学に入りました。大学院の修士までは研究をしたかったんですが、うまく論文が書けず行き詰まった。「うまく書けないな」「好きなのに書けない」とジレンマに陥ったときに、翻訳をやってみればこのスランプを打破できるのかなと思いました。(いろんな研究者の方がいらっしゃいますが)研究は自分の論じたい方向に沿って戯曲を読むこともでき、深く考えるところと考えないところがあるんです。でも翻訳は始めたら逃げ場がなく、あらゆる人物について、自分が全て一番分かってないといけない。普段の自分だったら、ただ読んでいるだけで深く考えないようなことも深く考えなくちゃいけない。自分の読み方そのものを変えることができると思って、博士課程に入ったぐらいから、翻訳の仕事を始めるようになった。翻訳をやり始めてまだ7~8年ぐらいなんですよね。同世代や僕より年下の俳優さんでも、もっと昔から舞台に立っている方も多く、翻訳家は「翻訳家先生!」みたいにすごく偉そうに扱われることが多いのですが、だいたい僕が一番芸歴が短いという。(笑)響さんは?
小笠原響(以下「小笠原」) 僕も両親が俳優なので、僕がお腹の中にいた時に母が俳優座劇場の舞台に立っていた。その後も両親の芝居のギャラでご飯食べさせてもらっていました。
佐藤 劇団員の方々にも面倒を見てもらっていたの?
小笠原 近所に劇団の人が住んでいて、お宅に遊びに行ったり、楽屋に連れて行かれたり。ちょっと拒否反応を起こしてしまったときもあった。芝居をやっている人は目つきもぎょろっとしていて、声も人より大きいし、なんだか怖くて。特に当時の俳優座はメイクもしているし、子供からすると魔界の世界ですね。両親からは「芝居をやると食えないから、お前はやるな」と言われていたので、ずっと演劇からは遠回りしていました。結局、一番見てきた世界が芝居だったので、大学3年生の時に親に「やっぱりやりたいです。」といいました。父はがっかりしていましたね。
※「オズのまほうつかい」スペシャル対談動画でも小笠原響の演劇との出会いを語っています。以下、リンクよりご覧いただけます
【小笠原 監修×演出振付 深堀絵梨 スペシャル対談】親と子のクリスマス・メルヘン『オズのまほうつかい』 - YouTube
Q 「ドクターズジレンマ」は、分かりやすく言うとどのような作品ですか?
小笠原 「ドクターズ」とあるように、権威のある医者たちが主人公を含め6人出てきます。そこに地位も名誉もまだない若くて才能溢れる画家が現れ、主人公の医者と対立します。医者と芸術家が火花を散らす物語になっており、そこが面白いところです。
小田島 しょうもなくろくでもない医者たちがいっぱい出てくる作品です。(一同笑い)テレビ朝日のドラマ『ドクターX ~外科医・大門未知子~』の中であったような「私、失敗しないので」を本気で言って取り繕う医者が出てきて、医者という専門職の裏側が見えてくる。善人も出てこなければ、邪悪な人も出てこないが、みんな真剣で、周りから見ると「しょうもないよね」というお医者さんたち。題名からすると「固い芝居かな」とも感じられますが、笑いに溢れたお芝居になると思います。俳優さんたちが笑わせてくれるお芝居になると、誓さんにプレッシャーをかけておきます。(笑)
佐藤 笑えるかどうかは翻訳次第ですね。(一同笑い)一言でいうと、とても誠実なんだけれども貧しいお医者さんと、とても才能があるんだけれども人間的に問題がある画家の、どちらの命を救うかという医者のジレンマです。
Q それぞれの立場で注目ポイントを教えてください。
小田島 バーナード・ショーという作家は、セリフの書き方が面白く美しい。言葉が整っているのに人間性を斜めから見て、皮肉を込めて風刺しながら、人間に対する温かみを失ってない。そういったユーモアが炸裂しているところが翻訳家としての見どころで、セリフの言葉に注目してほしいです。
佐藤 旧訳の翻訳(「戯曲 医者のジレンマ―悲劇 田村敏夫訳」)とはかなり違うんですか?
小田島 中身が変わっているというわけではありませんが、できるだけ若者であれば若者らしい言葉にするなど、それぞれのキャラクターがはっきりと分かりやすくなるような言葉にしています。あとは、舞台の上で話して面白く聞こえるような言葉のチョイスに気をつけて翻訳しています。
佐藤 読み合わせ稽古をした際に、1903年の昔の話ではあるが、全然古さを感じなかった。
ーー読み合わせ稽古では6人のお医者さんがそれぞれの個性を出して読んでいらしたと思います。いかがでしたか?
小笠原 それぞれの風合いが色とりどりに出ていて、せんがわ劇場の空間で渡り合ったときに多彩な味が出るなと思いました。
佐藤 響ちゃんは、出演者全員と仕事したことがあったの?
小笠原 若手3人(石川湖太朗、なかじま愛子、星善之)は初めて。あとは全員と仕事してる。
佐藤 キャスティングが見事で、まさにハマリ役だった。髙山さんの包容力があるがいい加減な感じや(清水さんは読み合わせにいらっしゃれなかったけど)とにかく喋るのが目に浮かぶんですよ。内田さんの堅物さ加減や、滋くんの本当に貧しくてかわいそうな感じ。山口さんの思い込んだら「これしかない」みたいなものが、皆さんのキャラクターに合っていて驚いた。
小笠原 僕も、自分で驚いた。
佐藤 大井川さんも大人しそうな方ですが、強く、才色兼備で芯があり、したたかでもある女性をどう演じるのかもすごく楽しみですし、石川湖太朗くんの嫌なやつさ加減も見事で。本当にこれは見てほしいと思いました。なかじまさんの、全然タイプの違う役を複数演じるところも面白かったし、星さんは(読み合わせの時は)残念ながらドイツからオンライン参加で声が聞けなかったのですが、とにかく役者陣がとても楽しみです。
ーーありがとうございます。注目ポイントは俳優ですね。ちなみに佐藤さんの役もすごく難しく、葛藤を抱えていると同時にとても面白くやりがいがあるなと思います。
小笠原 読み合わせ稽古のときに、誓さんと湖太朗くん(リジョンとルイス)のやり取りや大井川さん(ジェニファー)との会話がとにかく面白くて。たくさん役が出てくるなかで、1対1の会話になったときに芝居がスリリングになるんですよね。そこが楽しみです。大劇場から小劇場までことごとく制覇し、酸いも甘いも舞台のことを全部知っている誓さんと若手でグッと上がってきた湖太朗くんが舞台でぶつかるところが見どころです。若手のパワーとベテランのパワーが拮抗してぶつかるシーンが用意され、医者役の俳優はそれぞれが独特のスキルを持っているんだけど、若手もそこにまっすぐぶつかってきてくれている感じがする。

小田島 皆さん、積んできた稽古や経験が全然違う方だと思うのですが、どのように稽古されるんですか?
小笠原 僕はこれだけの素材を集めて、どう料理していくかというところに尽きるのだと思っている。有名シェフがよく言う「素材の味を生かして」って。個々の育ってきたバックグラウンドも含めて、持ち味を最大限に引き出して、刺激的な時間と場所を創り出していくというのが最大の使命かなと。今回、チャーハン・ラモーンさんがデザインしたチラシが物語を端的に表現してくれている。主役の誓さんが演じるサー・コレンゾー・リジョンという医者が上から見下げて、その先に若い才能の塊の2人がいる。この芝居を象徴してくれていて、チラシを見たときに「チャーハンさん天才」と思った。才能あふれる若者たちの命の鍵を、1人の男が握っていることがわかり易く伝わってきて。ある意味で神の領域に踏み入ってしまったドクターのジレンマ。科学を手中に収めた人類の驕りが、例えば現代の地球温暖化や核の脅威など、今の問題に繋がっていくのだと思う。

ーー力を持ってしまうと「選択」できることになる。その力をどう使うか。どのような倫理感でそれを選択するかというジレンマは、広くいろんな人に分かりやすいトピックですよね。
小笠原 今しきりに言われているモラハラも社会で鍵を握ってしまった人のあり方が問われているんじゃないか。この芝居の場合は、ある医者が命の鍵を握ってしまうが、それは医者だけじゃなくて世の中をリードする指導者、権力者に当てはまっていくことなんだと思う。
Q ズバリ演劇の面白さとは?
小田島 当たり前ですけど家にいると家の中だけ。でも劇場に行くとなると、1日の中の非日常的なイベントになる。例えば「休日どう過ごす?」あるいは「仕事を早めに終えて、その後のフリーな時間をどう過ごす?」と考えたときに、1日を楽しむために劇場に行くっていう行動があっていいのかなと思っています。自分のテリトリーから出て、あるいは普段の行動からちょっと違うことをしてみて、楽しいことや知らなかったものに触れてみる。イベントは家の中でもあるかもしれないけど、外に行って楽しむイベントはやっぱりウキウキするし、すごく素敵なことだなと思っています。「ドクターズジレンマ」を見て、その後、深大寺の湯守の里に行ってもいいですね。僕が劇場に行く面白さってそういうところだなと思います。
ーー確かに「ドクターズジレンマ」で言えば、せんがわ劇場の中に入れば120年前のイギリスを感じられ、ショートトリップができる。素敵なことですよね。
佐藤 舞台は目の前で見られ、生の人が喋って動いて、それがダイレクトに入ってくる。役者の僕らからすると、お客様の反応を直に感じながらお芝居ができる面白みがあり、お客様としても同じ空気を吸いながら、一緒に参加できる面白さがあると思う。それも1回限りで、その場限り。巻き戻しもできないし、途中でトイレに行っても芝居をストップすることもできない。1回のライブという非日常的な面白さ。わざわざ時間をかけて、お金もかけて、他のお客さんと共有しながら笑ったり。そういう面白さが演劇にはあるんじゃないかな。
ーー芝居は1~2か月前から練習しますが、本番になったら相手役とお客様の空気とかですごく変わりますよね?練習したことを毎日同じようにただやっていると思われちゃうと、実はそうじゃない。その日のお客様や相手役によっても生き物のように違う。だからこそその1回に立ち会うという面白さを知ってほしいですよね。
佐藤 内容だけじゃなく、1回しか見ないと分からないことも、2回見ると分かることはたくさんありますよね。僕も野田秀樹さんの芝居を見たときに、パンフレットの中で「演劇の面白いところは、間違うことだ」ということが書かれてあり、セリフを間違えたり、何か間違えたりするのが面白いんだと。創り手からしたらミスだったりすることも、生でしかありえないこと。カットをかけて撮り直すこともできない。それも含めての演劇の生の舞台の面白さなんだと思う。
ーーミスもあるかもしれないし、逆に言うと本番でお客様が入ったら急に今までに練習してきた以上の何かが生まれたり、初日マジックみたいなこともあったりしますもんね。
佐藤 稽古の方が良かったということはまずない。
小笠原 俳優さんは、お客様と触れた時に化学反応が起きる。稽古は仕込みに過ぎず、お客様の前に来たときに、どんな香りを出して、どんなふうに膨らんでいくのか。生であることが魅力であって「新鮮さ」があるんですよね。映画や動画、映像はあらかじめできたものを見ることになるけれど、舞台はその場でお客様を相手にしながら創っていくもの。テレビ番組でタレントさんが漁師の船に乗って、釣りたての魚を捌いて「美味しいですね」というのがある。農園に行って捥ぎたての野菜を食べたり。ああいう美味しさというのはそこ行かないと味わえないもので、芝居は似たところがある。劇場に足を運ばないと味わうことができない。
小田島 世の中に劇場はたくさんありますが、その中でも”せんがわ劇場の魅力”は何だと思いますか?
小笠原 せんがわ劇場は、目の前で新鮮なものが味わえる“超贅沢空間”。
小田島 客席と舞台とが近く、物語の世界に没入できる空間でもありますね。お客様と登場人物が一体感を味わえる。
佐藤 手を伸ばせば届いてしまうような距離ですもんね。今、私は地方公演の最中ですが、劇場が変わっていくと、劇場に合わせたような演技をしなくてはならない(1000席規模であればそれに合わせて大きな声を出したり)。でもせんがわ劇場だったら、会話しているようなことでもお客様に届くし、細かい表情も、伝えられる。僕はどっちの劇場の規模も好きですし、今からすごく楽しみです。先日久しぶりにせんがわ劇場に来て「こんなに良い劇場だったんだ」って改めて思いました。
ーー一番後ろの席にいても、舞台上の役者さんの息までちゃんと聞こえ、感じられる。すごい臨場感ですよね。
小笠原 せんがわ劇場は客席のレイアウトが自由に変えられるんです。今、美術の乘峯雅寛さんとも打ち合わせを進めているところですが、お客さんとの垣根なく、俳優と一体になって感じられる劇場空間を作りたいと一生懸命プランを練っています。
小田島 俳優さんのエネルギーをすごく感じやすい劇場。あとやっぱり深大寺の“湯守の里”、仙川の”湯けむりの里”が近いってのがいいところですね。
(一同笑い)
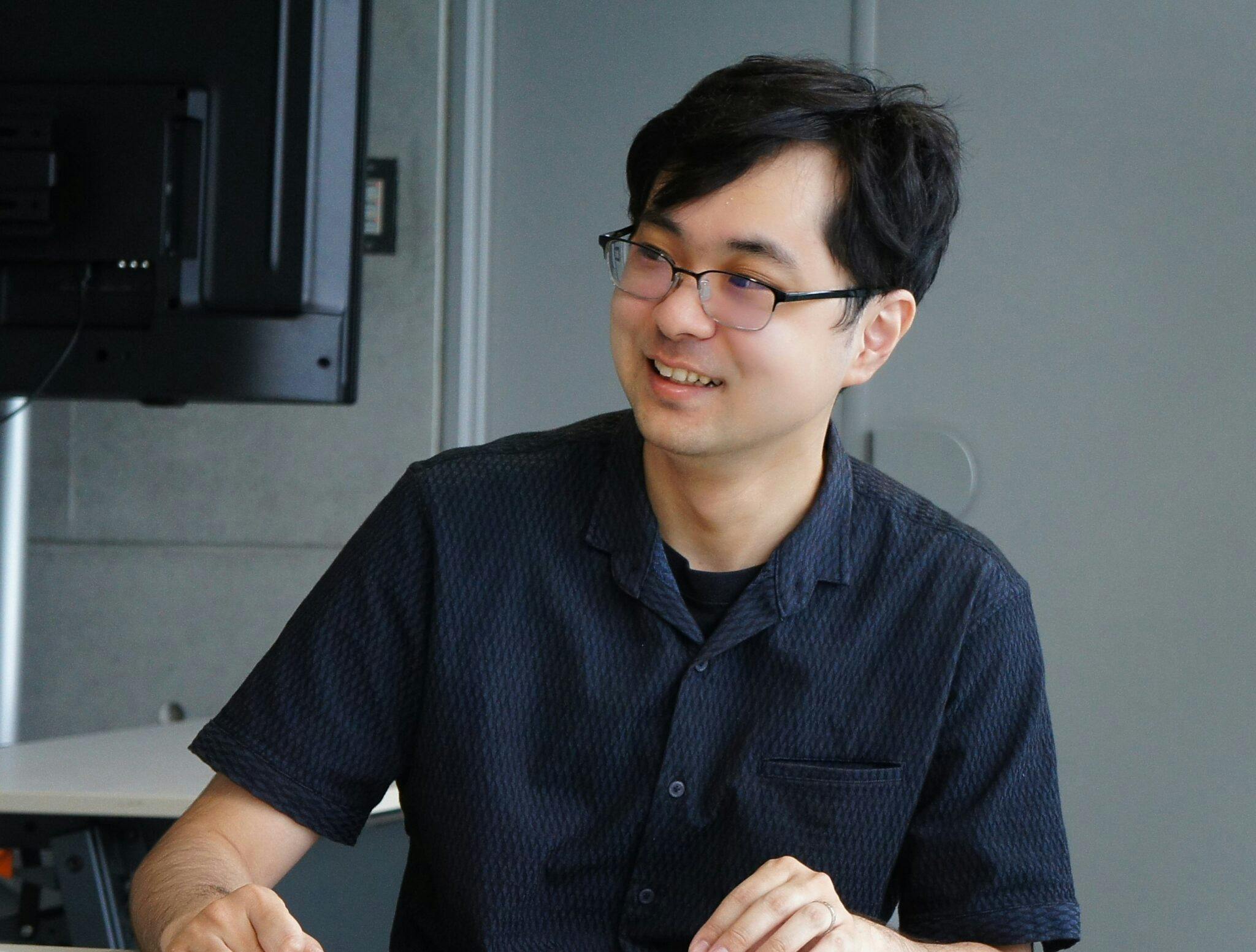
Q バーナード・ショー作品を始め、近代劇の面白さを教えてください。
小田島 バーナード・ショーは1925年にノーベル文学賞を取っています。近代劇はバーナード・ショーやオスカー・ワイルド、サマセット・モームという人がいます。この作家たちはセリフの文学性が高く、美しい英語を書かれます。演劇の文学性をすごく感じることができるのが醍醐味です。ただ、この「ドクターズジレンマ」は、英語がとても難しいんですよね。僕がジレンマになってしまいそうです。特にバーナード・ショーの英語は、言葉の表面上の意味も、裏側の意図や皮肉、ユーモアというものを解釈するのがとても難しい。「これこういう意味だったんだ」や「これこういう意図でこのセリフがあるのか」と解釈できたときに、すごく戯曲として美しく面白いと感じます。演劇の文学性や芸術性をすごく体感できるのが近代劇の面白いところですね。
ーー小笠原さんも翻訳劇を沢山演出されていますが、近代劇をやるときに気をつけていることは、ありますか?
小笠原 近代劇の面白いところは、例えば今回の作品も100年ちょっと前の作品ですが、現代と比べて、生活習慣や国の違いはありつつも、100年経っても変わらないことがあるんだということ。「人間っていつまでたっても変わらないのね。」と普遍性の上塗りができる。時代の隔たりの中で、変わらない生身の人間がいることが魅力だと感じる。単純に古い芝居と言ってしまえばそれでおしまいなんだけれども、翻訳の仕方や言葉の選び方、俳優の演技、衣装のスタイルなどから現代性を持たせることができる。何年経っても変わらない人間の本性みたいなものが見えてくるんじゃないかなと。今と照らし合わせて楽しめるようにアプローチしていきたい。
小田島 先ほどバーナード・ショーの文学性が醍醐味と言いましたけど、近代劇や文学性という言葉を出すと「すごく難しいな」というイメージになってしまいそうですが、今回の舞台は「文学って難しいものじゃなくて楽しいもの」あるいは「文学を通して社会が分かりやすく見えてくるよ」ということが実感できる舞台だと思います。翻訳も現代の人が聞いて面白いと実感できるような言葉を今探っている最中です。決して置いていかれるような日本語にはしないように翻訳していますし、生の舞台で人間性を楽しみながら見るにはうってつけの作品な気がします。
ーーシェイクスピアのように、あえて難しい言葉でやり取りすることによる面白さもあると思います。それに俳優さんが演じるとすごく難しい芝居も、そうじゃなく感じたりしますよね。
佐藤 また俳優のハードルを上げていますね。(笑)
小笠原 セリフに文学性があったとしても、多分今回集まった俳優さんたちはそれを実感としてお芝居にしてくれるはずです。そうするとお客様は本を読むような文学性を感じるというよりは、気がついたら、文学的な言葉を浴びていたという形になるんじゃないかな。
佐藤 例えば家でテレビドラマを見て、今、現代の本当にリアルなやり取りを観ている人が、ちょっと違うものに触れられるいい機会にもなるんじゃないかなと思います。
ーーそれぞれの演劇の出会いから「ドクターズジレンマ」の見どころまで、たっぷりお話いただきました。ありがとうございました。せんがわ劇場としても芸術監督が就任、演出する公演は1作目となります。これまでに演劇を見たことがない方から長年の演劇ファンの方まで、楽しんでいただける作品になること間違いなし。多くのお客様にご来場いただきたいですね。
臨場感たっぷり”超贅沢空間”のせんがわ劇場で、皆様のご来場をお待ちしております。

【「ドクターズジレンマ」のチケットの発売日はアートプラス会員:9月3日(火)、一般:9月10日(火)から】
客席数が少ないため、お早めにご予約ください。
↓芸術監督演出公演「ドクターズジレンマ」公演詳細は以下のリンクをクリックしてください
